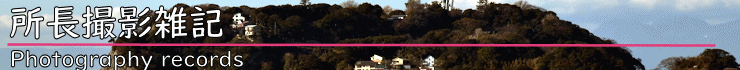2023年3月24日 鵜沼宿と名古屋の古い町並みを見る
.jpg)
この日は友人であるMr.KとMr.Sで岐阜と愛知で歴史散策。まずは新幹線で名古屋駅で下車し、在来線ホームへ向かうと、すっかり中央本線の主力車両となった315系に出会いました。
.jpg)
最初の目的地は、中山道の鵜沼宿。若干遠回りになりますが、岐阜経由で向かいます。こちらは東海道線の313系。
.jpg)
一方、こちらは殆ど313系と同じ顔つきですが、高山線のディーゼルカーであるキハ25形。上部の前照灯や種別表示器が無いのが、313系との外観上の差異。
.jpg)
車内の様子。オールロングシートで、ほぼ313系ですね。
.jpg)
岐阜駅に入線する313系8両編成。
.jpg)
続いて新型車両であるHC85系による特急「ひだ」を初撮影。
.jpg)
さて、岐阜に来た最大の目的が、2019(令和元)年からJR岐阜駅北口で保存されているモ513号。2005(平成17)年に廃止された名鉄の岐阜市内線などで活躍した車両で、1926(大正15)年に製造されたモ510形の生き残りです。元々は金公園で保存されていましたが、かつて停留所があった岐阜駅前に引っ越してきました。
.jpg)
路面電車があった頃の景観が少し再現され、非常に良いですね。
.jpg)
.jpg)
さて、岐阜と言えば織田信長が本拠地とした場所の1つで、岐阜バスでもPRしていました。
.jpg)
このまま岐阜市内を観光したいところではありますが、時間の都合で名鉄へ。こちらは2300系。2200系の6次車といった位置づけの車両です。
.jpg)
さて、我々が乗車するのは各務原線。地上ホームから出発します。留置線には6500系がいました。

ちなみに、かつては美濃町線が発着していた場所です。(2005年2月15日撮影)
.jpg)
それでは9500系に乗車して、出発。
.jpg)
鵜沼宿駅で下車すると、この付近で並走する高山本線のHC85系特急「ひだ」の通過に遭遇。
.jpg)
少し歩いて、中山道の鵜沼宿を散策します。鵜沼宿は江戸の日本橋から数えて中山道で52番目の宿場町で、江戸時代は尾張藩領でした。現在も古い町並みが残り、その保全と整備活用が積極的に進められ、中でも近年は町屋館(旧武藤家住宅)の修復、脇本陣の復原等が行われ一般公開されています。
上写真は丹羽家住宅【国登録有形文化財】。1930(昭和5)年築で、かつては旅籠を営み、「大坂屋」という屋号でした。
.jpg)
安田家住宅(若竹屋) 【国登録有形文化財】
1930(昭和5)年築。かつては旅籠を営み、「若竹屋」という屋号でした。1階・2階に格子を入れるなど、古風な造りとなっています。
.jpg)
坂井家住宅(丸一屋) 【国登録有形文化財】
1894(明治27)年築。正面に切妻造の破風をつけた式台玄関を設ける格式高い造りです。敷地の南東にある土蔵は2棟が合体して1棟の姿になっています。
.jpg)
中山道鵜沼宿脇本陣
2010(平成22)年復元。江戸時代末期に描かれた「鵜沼宿家並絵図」などを元に、鵜沼宿の脇本陣を務めた坂井家の建物を再現したもの。本陣と比べて規模は小さいものの門と玄関、上段の間を備えています。また、隣家からの防火壁である「うだつ」を備えています。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
古い町並みを保全するだけではなく、脇本陣の復元まで…すごいですね。
.jpg)
二ノ宮神社拝殿 【国登録有形文化財】
鵜沼西町の村社で、祭神は国挟槌命(クニサヅチノミコト)。拝殿は明治時代後期に建築されたものです。写真左下の穴が開いている部分は横穴式石室。実はこの神社、6〜7世紀ごろに造られた、直径29mの円墳の上に築かれています。
.jpg)
菊川酒造(本蔵・一号倉庫・二号倉庫) 【国登録有形文化財】
中山道に面して建つ本蔵は大正時代後期の建築で、土蔵造り2階建。一号・二号倉庫は明治時代後期の建築で、一号倉庫は小屋組にキングポストトラスを用い、二号倉庫は登梁の和小屋を用いているのが特徴です。
.jpg)
.jpg)
中山道鵜沼宿町屋館 【各務原市指定文化財・景観重要建造物】
中庭を囲むように主屋、東側の附属屋、西側の離れの三棟から成ります。江戸時代は「絹屋」という旅籠を営み、1883(明治16)年から「鵜沼駅三等郵便局」を経営します。主屋は1891(明治24)年の濃尾震災で倒壊し、明治時代末に再建されました。
.jpg)
旧大垣城鉄門 【各務原市指定重要文化財】
蘇原の安積家の門として使われてきたものを2009(平成21)年に移築したもので、その際の解体調査の結果、土台に墨書が発見され大垣城本丸の門であったことが判明しました。形式は高麗門で、正面に短冊状の筋鉄(すじがね)が張られています。それにしても、同じ岐阜県内とは言え、こんな場所に大垣城の遺構が…。
.jpg)
.jpg)
高札場も再現されています。
.jpg)
問屋場跡には、当時の尾張藩領(鵜沼地区南部)と各務村の境を示した傍示石が移設されています。
.jpg)
そして、今度は徒歩で新鵜沼駅に向かおうと歩くと、またHC85系に出会いました。
.jpg)
「かかみちゃん」マンホールを発見。各務原人参のマスコットキャラクターだそうです。
.jpg)
さて、名鉄の新鵜沼駅に到着。駅の外から、少々撮影するとします。
.jpg)
2200系が発車!
.jpg)
3100系の新塗装をゲット。
.jpg)
犬山城の遠景を撮影。
.jpg)
以前は鉄道道路併用橋だった犬山橋。
.jpg)
.jpg)
ここでも名鉄を撮影しますが、犬山橋の武骨な雰囲気が良い味を出してくれます。
.jpg)
.jpg)
名古屋に向かうために新鵜沼駅へ。ここで見かけた3500系は更新車で、種別・行先表示がフルカラーLED化されていました。
.jpg)
それでは、2200系に乗車して金山駅へ。
.jpg)
JRと名鉄、さらに名古屋市営地下鉄(名城線・名港線)接続する金山駅は交通結節点として「金山総合駅」と愛称的に表示されますが、他都市では見られないユニークな表示ですね。
.jpg)
商業施設も多く、名古屋でも有数のターミナルとなっています。
.jpg)
金山駅から地下鉄名城線に乗り換え、名古屋城駅で下車。2023(令和5)年4月1日に市役所前駅から改称されたもので、観光客としてはわかりやすくなりました。構内には、かつての名古屋城を描いた絵図が展示されています。
.jpg)
こちらが名古屋城…ではなく、愛知県庁。1938(昭和13)年に建築されたもので、渡辺仁と西村好時が基本設計を行い、愛知県内務部営繕課が実施設計を担当。地上六階地下一階、一部七階建で、外観は異なるタイル張による三層構成。そして、名古屋城大天守を思わせる破風付の入母屋造屋根を載せているのが特徴です。このような、西洋的な様式と和風の意匠を融合した建築は、当時流行したデザインで、「帝冠洋式」と総称されます。
.jpg)
隣接して名古屋市役所が建っているのですが、こちらは1933(昭和8)年築。コンペで金賞となった平林金吾の案をもとに、名古屋市土木部建築課が実施設計を行いました。鉄骨鉄筋コンクリート造、地上五階地下一階建で、外観はタイルやテラコッタで飾った上で、塔屋などを瓦屋根風の意匠とした、こちらも帝冠洋式の1つです。なお、愛知県庁、名古屋市役所ともに国指定重要文化財です。
.jpg)
さて、名古屋城は久しぶり訪れたのですが、「金シャチ横丁」という飲食・物販の商業エリアが2018(平成30)年3月29日にオープンしていました。こちらは、「義直ゾーン」と呼ばれるエリアで、江戸時代の商家を思わせる木造純和風建築が建ち並んでいます。以下にも観光向けといった感じですが、江戸時代の雰囲気を感じつつ、手軽に食事ができるのは有難いです。
.jpg)
こちらは「宗春ゾーン」で、建物はガラス面を大きく装った明るいモダン和風建築となっています。
.jpg)
ちなみに「義直ゾーン」では、商業施設の由来となった「金シャチ」が飾られています。
.jpg)
さて、名古屋城正門から入城します。藩主や年寄職など一部の家臣しか出入りできない格式高い門で、元々は榎多御門(えのきだごもん)がありましたが、1891(明治24)年の濃尾大地震で大破。このため1910(明治43)年には旧江戸城内の蓮池御門を移築しますが、戦災で焼失したため、1959(昭和34)年に再建されました。
.jpg)
西南隅櫓は、1612(慶長17)年築で国指定重要文化財。
.jpg)
表二の門も1612(慶長17)年頃築で、国指定重要文化財。
.jpg)
.jpg)
本丸表一之門跡。写真も残っているのですから、将来的に復元してくれないでしょうか。
.jpg)
さて、今回の主目的は新たに復元が完了した本丸御殿。
.jpg)
元々は1612(慶長17)年に建築が始まり、1615(慶長20)年に完成しました。当初は初代藩主、徳川義直の住まいでしたが1620(元和6)年に二之丸御殿へ住まいも政庁も移したため、将軍が上洛の際に宿泊する御成御殿(おなりごてん)として使われるようになります。特に、1633(寛永10)年に三代将軍・徳川家光の上洛に先立ち増築が開始され、翌年に上洛殿や湯殿書院(ゆどのしょいん)、黒木書院などが完成。
.jpg)
戦災で焼失しますが、狩野貞信(かのうさだのぶ)や狩野探幽(かのうたんゆう)など狩野派による障壁画は別に保管されていたため焼失を免れ、2018(平成30)年に木造で復元され、障壁画などは当時の輝きを再現して復元模写されました。
.jpg)
玄関(一之間)
.jpg)
.jpg)
表書院(手前:一の間、奥:上段の間)
.jpg)
旧二之丸東二之門 【国指定重要文化財】
1612(慶長17)年頃築。高麗門形式で、本来は東鉄門と呼ばれる二の丸東の枡形門の外門でした。愛知県体育館の建築に伴い、現在は本丸東二之門跡に移建されています。
.jpg)
不明門
1978(昭和53)年復元。本丸北側と御深井丸(おふけまる)をつなぐ門で、通常は施錠され厳重に管理されていました。
.jpg)
乃木倉庫 【国登録有形文化財】
明治初期に建てられた煉瓦造りの旧陸軍の火薬庫で、西北隅櫓の近くにあります。角を石積み風に造り出しているのが特徴です。乃木希典が1872(明治5)年頃に名古屋に赴任したことにちなんで、後にこの名前で呼ばれるようになりました。
.jpg)
さて、名古屋城を出て東へ少し歩くと名古屋市政資料館があります。1922(大正11)年に建築されたネオ・バロック様式のレンガ造建築物で、元々は名古屋控訴院・地方裁判所・区裁判所庁舎として使われました。戦後は名古屋高等・地方裁判所として使われますが、1979(昭和54)年に現在の三の丸へ移転。1984(昭和59)年に国の重要文化財に指定されたのち、1989(平成元)年から名古屋市市政資料館として一般公開されています。
.jpg)
控訴院は日本全国に8つ建設されましたが、庁舎が現存するのは本建物と札幌控訴院(札幌市資料館)のみです。また、レンガ造りの大規模建築としては国内最末期のものとして貴重なものです。
.jpg)
御覧のとおりの華麗な内装なので、ドラマ撮影等でも使用されます。2024(令和6)年のNHK連続テレビ小説「虎に翼」でも使用され、ドラマでの主役は日本初の女性弁護士の一人として活躍した三淵嘉子(1914〜84年)をモデルとしているのですが、実際に1952〜56年までここで働いていたとか。
.jpg)
明治憲法下の法廷(再現)。創建時の控訴院第2号法廷を再現したもの。裁判官と検察官が同列に並んでいるのが当時の特徴です。
.jpg)
陪審法廷(再現)。昭和初期に採用された陪審制度に基づく法廷を再現しています。
.jpg)
こちらは控訴院の会議室だった場所で、重厚な調度品が置かれています。内装の特徴として、腰を羽目板張りとし、合板を用いていますが、これは日本で合板を使用した初期の例です。また、壁と天井は漆喰塗りの上に紙張り仕上げとし、さらに天井は中央部を一段高くしてシャンデリアを吊るしています。また、北側に奉安所が置かれています。
.jpg)
雑居房も残されています。
.jpg)
名古屋市政資料館の東側である白壁・主税・撞木町には、尾張藩の中級武士が暮らした場所。流石に当時のままの建物はあまりありませんが、古い町並みが残っています。
.jpg)
カトリック主税町教会。正面玄関ポーチを構成している礼拝堂は1904(明治37)年築。下見板張りの洋風建築物である司祭館は1890(明治23)年頃築。
.jpg)
これは古い・・・わけではなく、百花籠(ひゃっかろう)という結婚式場です。和風なのか教会なのかよく分かりませんが、意外と好きなアンバランス感です。
.jpg)
旧春田鉄次郎邸。1924(大正13)年築で、陶磁器貿易商として成功し、太洋商工株式会社を設立した春田鉄次郎が建築家の武田五一に依頼し建てたものです。
.jpg)
旧豊田佐助邸 【名古屋市指定有形文化財】
1923(大正12)年または1915(大正14)年築。発明王として名高い、豊田佐吉の弟である豊田佐助の邸宅で、白いタイルが印象的な洋館と、和館で構成されています。
.jpg)
料亭か茂免。尾張藩の中級武士であった安藤十次郎邸の跡地に、京都の紙問屋だった中井巳次郎が名古屋別邸として建てた屋敷で、1928(昭和3)年に創業した「か茂免」が、戦災で被災したあとにここで営業を再開したものです。
.jpg)
旧豊田家門・塀。1918(大正7)年築で、門は薬医門形式、塀は黒色漆喰壁、竪羽目板腰壁です。豊田佐吉の婿養子で、豊田自動織機初代社長やトヨタ自動車工業初代社長などを歴任した豊田利三郎の屋敷跡で、敷地内はマンションになっています。
.jpg)
主税町長屋門。江戸時代に造られた名古屋の武家屋敷の長屋門で、当時と変わらぬ場所に現存する唯一の例です。
.jpg)
.jpg)
文化のみち二葉館として利用される川上貞奴邸。日本初の女優と謳われた川上貞奴と、電力王と称された福沢桃介が共に暮らした和洋折衷の近代建築で、元々は現在地よりも少し西北、出来町通りの北(東二葉町)にあったものを移築保存したもの。
.jpg)
旧井元為三郎邸(現・文化のみち橦木館) 【名古屋市指定有形文化財】
大正末期〜昭和初期の建築で、輸出陶磁器商である井元為三郎の邸宅でした。
.jpg)
さて、流石に街歩きも疲れまして名古屋駅に戻ります。中央線ホームには211系8両編成が停車していました。
.jpg)
その脇をEF64 1049号機を先頭とする重連貨物が通過。
.jpg)
名古屋駅でもHC85系を撮影。
.jpg)
最後に「ひつまぶし」を食べて〆としました。本当によく歩いた1日でした。