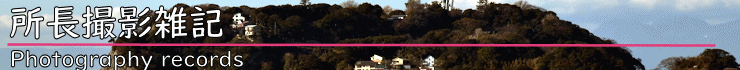2024年5月20日 「スペーシアX」に乗車し、栃木・足利を散策

この日は前に配属されていた職場の人たちと一緒に栃木と足利の古い町並みなどを散策することに。まずは東武鉄道の浅草駅に行くと、200系「1800系カラーリング」が停車していました。

そして、東武鉄道の新たなフラッグシップトレインである「スペーシアX」に乗車。

車内カフェを初めて利用し、車窓を楽しんでいるうちにあっという間に栃木駅に到着しました。

栃木市は古い町並みが残り、2022年3月9日の訪問以来となりますが、この時は撮影する列車のタイミングで時間が殆どなく、撮影出来なかった建築が多数…。ということで、今回はじっくりと歩きます。まず、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている、日光例幣使街道沿いの嘉右衛門町通りを見ていきます。
まず、こちらはシェアオフィスや物販スペースなどとして使われているKAEMON BASE。みそ工場跡地の伝統的建造物14棟を改修したものだそうです。

こちらは「交流館」として改修されたもの。


平澤商事

岡田記念館。このエリアを開拓し、代々の当主が嘉右衛門を襲名した岡田嘉右衛門の屋敷を一般公開した施設で、現在も岡田家が保有しています。

ちなみに、江戸時代には旗本である畠山家が、この場所の支配のために岡田家を郷代官としていました。


この日は公開していませんでしたが、岡田家翁島別邸。


大貫邸。1834(天保5)年築。

舘野家店舗。住宅主屋とともに1932(昭和7)年築で国の登録有形文化財です。 さて、このエリアからは少し離れて周囲を歩きます。

こちらは1913(大正2)年建築の栃木病院。

旧・栃木町役場庁舎。1921(大正10)年に建てられたもので、栃木市の有形文化財。2014(平成26)年まで約90年間にわたり、栃木町、ついで栃木市の庁舎の1つとして使われ、2019(平成31)年から約2年をかけて改修。建築当初の姿に復元され、現在は栃木市立文学館として使われています。ちなみに隣接地(旧栃木市役所本庁舎跡地)には栃木市立美術館が誕生し、一帯が文化ゾーンになっています。

ちなみに栃木市は栃木県の発祥の地。1884年に県庁が宇都宮へ移転するまで、ここが栃木県における行政の中心でした。

栃木高校記念図書館(養正寮)。1914(大正3)年築で、国登録有形文化財です。

栃木高等学校講堂。1910(明治43)年築で、国登録有形文化財です。


続いて巴波川沿いへ。こちらは、国登録有形文化財の横山郷土館店舗及び住居で1909(明治42)年築。横山家は巴波川の舟運を利用して苧麻問屋を営み栄えた家で、こちらの建築は前面を店舗,後方を住宅としたうえで、さらに店舗は北半を問屋,南半を銀行とているのが特徴です。
 こちらは「ダイニングカフェ&居酒屋 とちえん」。1926(大正15)年築の元産婦人科の建物をリノベーションしたものです。
こちらは「ダイニングカフェ&居酒屋 とちえん」。1926(大正15)年築の元産婦人科の建物をリノベーションしたものです。

栃木市指定有形文化財の蔵の街市民ギャラリー。近江出身の豪商「善野家」の土蔵として、文化年間から天保年間にかけて順次建築されたもので、困窮人対策として金銭や食糧などを放出したことから「おたすけ蔵」として親しまれました。

1904(明治37)年築の「とちぎ蔵の街観光館」。もと「八百金」の名で知られた荒物・麻苧問屋田村家の店舗です。

明治時代後期築の雅秀店舗。国登録有形文化財で、旧例幣使街道の西木戸があった幸来橋の東にあります。googleのストリートビューで見る限り、最近は使用されていない感じが…。

塚田歴史伝説館と巴波川。栃木市を代表する景観です。塚田歴史伝説館は、弘化年間(1844年〜1848年)から木材回漕問屋を営んできた豪商邸宅を資料館として改修したものです。

さて、栃木駅に戻って来ました。今度は211系に乗車して、両毛線で足利駅に向かいます。(上写真は反対方向の小山行きの列車)

足利駅は1933(昭和8)年築で、同時期に建てられた両毛線の駅舎が高架化等もあり改築される中、現在のその姿をとどめています。

さて、足利学校に到着しました。日本最古の学校として知られ、その創建は奈良時代の国学の遺制説、平安時代の小野篁説、鎌倉時代の足利義兼説など諸説ありますが、室町時代に関東管領の上杉憲実(1410頃〜1466年)が再興に尽力し、鎌倉の円覚寺から僧快元を庠主(しょうしゅ=校長)として招いたり、現在国宝に指定されている蔵書を寄贈するなど、繁栄の基礎を築き、1872(明治5)年に閉校するまで使われました。
上写真は学校門で、1668(寛文8)年築。扁額「學校」の文字は、同年に明の書家である蒋竜渓(しょうりゅうけい)が来日した時の書を、当時の江戸国史館助教授の狛高庸(こまたかやす)が縮模したもの。

杏壇門。1668(寛文8)年築。1892(明治25)年に学校西方からの火災で屋根、門扉が焼けたため修築。扁額「杏壇」は紀伊徳川家第10代当主の徳川治宝(1771〜1852)の書。

孔子廟。1668(寛文8)年築。正式には大成殿と云い、1535(天文4)年に造られた孔子座像を祀るほか、学校創始者とも云われる小野篁公像を安置しています。

方丈(左)と庫裏(右)。こちらは復元されたもの。


北庭園


木小屋。牧や農具を置きました。

土蔵

衆寮(しゅりょう)。寮として使われました。

続いて北側にある足利氏館(鑁阿寺)へ。源義家の孫である足利義国・足利義兼親子が鎌倉時代の初めに築いたと云われ、1196(建久7)年に義兼は館内へ持仏堂を建立。13世紀前半には義兼の子である足利義氏が、義兼の追善供養のため堂塔伽藍を開始し、邸内の寺院化が本格的に始まります。足利義兼の法名である鑁阿(ばんな)から、鑁阿寺と称しました。
上写真は太鼓橋(反橋)と楼門。栃木県指定文化財です。

国宝である本堂(大御堂)。1299(正安元)年に足利貞氏(足利尊氏の父)が建立したもので、1407(応永14)年から1432(永享4)年にかけて修築。江戸時代中期に正面向拝が改造されています。本尊は大日如来。

国指定重要文化財の一切経堂。足利義兼が創建した後、1407(応永14)年に関東管領の足利満兼が再建したもの(※現地看板及び鑁阿寺ウェブサイトの記載。文化庁の国指定文化財等データベースでは、江戸時代初期の建築と記載)。内部にある八角の輪蔵にて、一切経二千巻余(黄檗版)を収蔵しています。

栃木も足利も非常に良いところですね。というか、栃木県は全体的に観光名所が多いのですが、日光を除けば全国的な知名度はイマイチなのが勿体ない…。