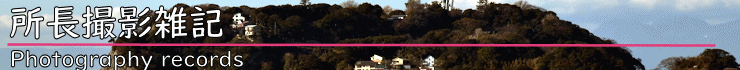2025年1月12日 近衛文麿ゆかりの荻外荘公園と大田黒公園・角川庭園をめぐる

この日は杉並区の荻窪エリアを散歩。内閣総理大臣を3度務めた政治家・近衞文麿(このえふみまろ)が、1937(昭和12)年の第一次内閣期から1945(昭和20)年12月の自決に至る期間を過ごした「荻外荘(てきがいそう)」が往時の姿に復元され、昨年12月9日から公開を開始したというので、見に行ってきました。

元々は、入澤達吉(いりさわたつきち)の荻窪別邸として1927(昭和2)年に建てられたもので、設計は伊東忠太(いとうちゅうた)。近衞文麿が購入し、戦後は吉田茂が一時使用したほか、近衛文麿の次男である近衛通隆氏が使用してきたそうです。


外観も近衛文麿が住んだ頃の姿に復元。

それでは、内部を見ていきましょう。


応接室。天井には龍が描かれた4枚の天井画が貼られています。


荻窪会談の舞台となった客間。今回の復元にあたり再移築された部分の1つで、写真2枚目は第2次近衛内閣発足を前にした、荻窪会談の際に撮影された写真。左から近衛文麿(次期総理)、松岡洋右(次期外相)、吉田善吾(海相)、東條英機(次期陸相)。この会談の後、日本は独伊と同盟を結び、南進政策を決めました。このほか、1941(昭和16)年10月に対米開戦を回避するための『荻外荘会談』なども開かれています。

1945(昭和20)年12月16日、「巣鴨拘置所」への出頭当日の早朝に近衛文麿が服毒自殺した書斎。当時の雰囲気を残しています。

近衛文麿着用の有爵者大礼服(複製)。公爵であった近衛文麿は、襟と袖が紫色の大礼服でした。

荻外荘と吉田茂。1947(昭和22)年から1948(昭和23)年にかけて、吉田茂が仮住まいとしていました。

続いて近くにある角川庭園へ。1955(昭和30)年に加倉井昭夫(1909〜1988年)の設計により建築された、角川書店の創業者で俳人だった角川源義氏(1917〜1975年)の邸宅(国登録有形文化財)を杉並区が譲り受けて、2009(平成21)年から公開しているものです。




さらに近くにある太田黒公園へ。日本で初めて音楽評論の分野を確立した、音楽評論家である大田黒元雄(1893〜1979年)の屋敷跡を杉並区が回遊式日本庭園として整備し、1981(昭和56)年に開園しました。


1933(昭和8)年に大田黒氏が仕事部屋として建てた「旧大田黒家住宅洋館」(国登録有形文化財)が残り、氏が愛用していたスタインウェイ社の1900年製造のピアノも展示されています。



このほか、荻窪駅から太田黒公園方面へ向かう途中には、西郊ロッヂング【国登録有形文化財】があります。こちらは1938(昭和13)年に建てられた高級下宿洋館。元々は東京都文京区本郷で下宿屋として創業し、関東大震災を契機に1931(昭和6)年に荻窪へ移転しました。2001(平成13)年に改修されて現在は賃貸住宅になっています。また、写真左奥は1931(昭和6)年に建てられた旅館「西郊」【国登録有形文化財】。いつか泊まってみたい・・・。

また、こちらは旧中田家長屋門。荻窪駅近くに残る長屋門で、現地には特に何の解説看板もありませんが、旧下荻窪の名主である中田家の建物だったとか。江戸時代に第11代将軍の徳川家斉が鷹狩を行った際の休憩所として使用するにあたって、農家の建物ではふさわしくないので、武家屋敷風の長屋門を造ったといわれます。また、明治天皇は明治16年に埼玉県飯能の近衛師団の演習の統監される際に立ち寄って以降、小金井に花見へ行く際に毎年立ち寄っていることから、「明治天皇荻窪御小休所」の石碑が建ちます。


荻窪駅に戻ると、特急が通過…。E257系5000番台による特急「開運成田山初詣八王子号」でした。色は変わりましたが、E257系といえば中央線ですね。


最後に新宿駅でE257系2000番台による臨時特急「下田水仙まつり号」を撮影。何かものすごく珍しいという雰囲気ではありませんが、一応記録…。